
不動産管理業務は、契約や修繕、会計処理など幅広い業務が重なり、担当者の負担が大きくなりがちです。加えて、作業量が多いにもかかわらず、紙やExcelに依存した運用が続くと情報が分散し、担当者ごとの管理方法にもばらつきが生まれます。結果、対応の遅れやミスが発生しやすくなり、オーナーや入居者からの信頼を損なう一因となります。
こうした課題を解消するには、電子化やデータの一元管理、自動化を通じて業務の流れそのものを見直すことが必要です。現場の負担を減らしながら、迅速で正確な対応と、経営判断の質を高める仕組みを整えることが求められています。
この記事では、不動産管理業務における非効率の背景と課題を整理し、業務効率化を実現するための具体的なアプローチやクラウド導入のポイントについて詳しく解説します。
不動産管理業務に効率化が求められる背景

不動産管理業務の効率化が求められる背景には、現場における慢性的な人手不足と、従来の管理手法に起因する構造的な問題があります。
契約や修繕、入出金といった日常業務は、限られた人員のもとで同時に進行し、担当者の負担は年々増加しています。さらに、紙やExcelを中心とした管理では、情報の共有や更新に時間がかかり、対応スピードが落ちやすいのが実情です。
結果として、属人化や引き継ぎミスが発生し、オーナー・入居者の期待に十分応えられないといったケースも少なくありません。
ここでは、こうした課題が生まれる背景と、不動産管理業務に効率化が欠かせない理由を整理します。
市場縮小や人材不足による負担増
日本の不動産市場は、少子高齢化や人口減少の影響で長期的に縮小が見込まれています。賃貸需要は地域によって二極化し、都市部では依然として高い需要がありますが、地方では空室率の上昇が課題となっています。
その一方で、市場が縮小しても管理業務の内容は多様化・複雑化しており、業務量が減るわけではありません。人材不足の影響もあり、1人の担当者が複数の業務を抱える状況が常態化しています。
現場の負担が高まる中で、限られた人員で安定したサービスを維持する手段として、業務効率化が不可欠な状況になっています。
アナログ管理の限界と属人化リスク
管理会社の中には、紙やExcelで業務管理を行っているというケースも少なくありません。こうしたアナログ管理は、複数の媒体やツールを併用するがゆえに、更新漏れや転記ミスが発生しやすく、正確性や迅速性を損ねます。
また、顧客管理が担当者任せになっていたり、スタッフそれぞれで異なる管理方法を取っていたりすると、業務のやり方がばらつき、引き継ぎのたびに混乱が生じます。結果として、対応遅れや情報の分断が起こり、オーナーや入居者からの信頼を損なうリスクが高まります。
こういった事態を防ぐためには、業務を標準化し、顧客管理・追客・対応履歴などの情報を一元管理することが欠かせません。
オーナー・入居者対応に求められるスピード感
不動産管理の現場でまず求められるのは、迅速で的確な対応です。オーナーは収支報告や修繕対応を早く知りたいと望み、入居者もトラブルや不具合への即時対応を期待しています。
一方で、紙やExcelなどによるアナログ管理では情報が分散し、問い合わせへの対応が遅れてしまうケースも少なくありません。
迅速な対応は、オーナーや入居者の安心と信頼を支える土台となるものです。業務効率化は、その品質を継続的に高めるために欠かせない取り組みといえるでしょう。
PM業務の非効率を生む代表的な課題
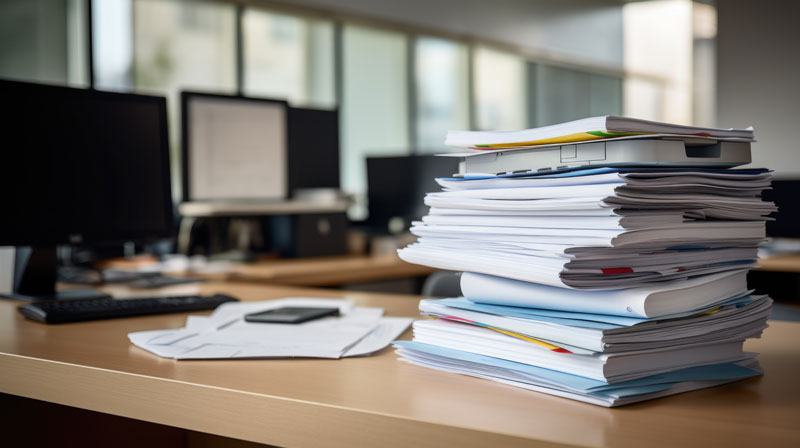
不動産管理業務の効率化が重要視されている一方で、現場では依然として紙やExcelによる運用が多く、構造的な非効率が残っています。
こうした状況では、いくら個別の業務を改善しても全体としての業務スピード・正確性を高めることはできません。結果として、オーナーや入居者への対応品質にも影響がおよびます。
ここでは、不動産管理業務の現場で特に顕在化しやすい非効率の要因を整理し、次に進むべき改善の方向性を考えます。
紙ベースの契約・更新手続き
契約や更新を紙書類で行う場合、押印や郵送、保管などの手作業が欠かせず、処理に時間と手間がかかります。その際、書類のやり取りが担当者間で分散すると、どの案件がどこまで進んでいるのか把握しづらく、確認や差し戻しに余計な工数が生じます。
さらに、契約書を紙で保管していると、必要な情報をすぐに取り出せず、トラブル発生時の対応が遅れることもあります。こうしたアナログ運用は、情報共有や進捗管理を不透明にし、結果的にオーナー・入居者双方への対応スピードを低下させる要因となっています。
修繕履歴や点検情報の分散管理
建物の修繕や法定点検は、資産価値を維持するうえで欠かせない業務です。しかし、その履歴や記録がExcelや紙ファイル、担当者ごとのメモなどに分散していると、物件全体の状態を正確に把握するまでに時間がかかります。
オーナーから「この物件の修繕履歴を確認したい」と依頼があっても、複数の資料を突き合わせなければならず、即答できないケースも少なくありません。
情報が整理されていない状態では、点検の更新漏れや履歴の抜け落ちが発生しやすく、管理の精度や報告スピードに影響を及ぼします。
入出金・精算業務の二重入力
入金確認やオーナーへの精算業務は、仕訳や照合作業を伴うため、担当者の負担が大きい業務のひとつです。特に、Excelなどによるアナログ管理では、物件数が増えるにつれて管理の煩雑さが顕在化します。
また、システムとExcelを併用して運用すると、同じデータをそれぞれのツールに入力する必要があり、更新のタイミングや内容にずれが生じやすくなります。その結果、送金や報告の遅れといったリスクが高まり、オーナーからの信頼を損なう要因となります。
部門・法人間での情報連携不足
不動産管理業務は、PM(プロパティマネジメント)だけでなくBM(ビルディングマネジメント)やAM(アセットマネジメント)といった複数部門が密接に関わります。ところが、各部門・法人が独自のデータベースやExcel、紙資料を用いて情報を処理していると、横断的な共有が難しくなります。
たとえば、BMが実施した設備点検の結果がPMに伝わらなければ、修繕手配が遅延し、テナント・オーナー対応に影響を及ぼすといったことが考えられます。
部門間の壁を解消し、共有ツールや統一された体制を整備しない限り、効率的な情報共有を実現することはできません。
レポート作成に時間がかかる
オーナーへの月次報告や社内向けの経営資料の作成は、不動産管理会社にとって欠かせない業務です。
しかし、契約・入出金・修繕といった情報がそれぞれ異なるシステムやExcelで管理されていると、必要なデータを集めて照合するだけでも多くの時間を要します。
また、担当者ごとにフォーマットや作成手順が異なる場合、整合を取るための修正や再入力も発生し、報告が後手に回りがちです。
報告が遅れると、オーナーへの信頼低下や社内での意思決定の遅れを招き、業務全体のスピードと正確性に影響を与えます。
業務効率化を実現する5つのアプローチ

ここまで見てきたように、不動産管理業務の非効率は、紙やExcelによる手作業や情報分断、属人化など、さまざまな場面に潜んでいます。
こうした構造的な課題を解消するには、単なる部分的な改善ではなく、業務全体をデジタルでつなぐ仕組みが欠かせません。
ここでは、PM業務の効率化を進めるうえで、特に効果的な5つのアプローチを取り上げ、具体的な改善の方向性について解説します。
①契約・申込の電子化
契約・申込プロセスを電子化することで、印刷・押印・郵送といった手作業を削減し、締結までのスピードを大幅に短縮できます。
電子契約システムを活用すれば、更新時のリマインドや承認フローを自動化でき、確認漏れや書類紛失といったトラブルも防止できるでしょう。
さらに、ペーパーレス化によって保管スペースやコストを抑えられ、必要な契約データをすぐに検索・共有できるようになります。
契約・申込手続きをオンラインで完結できるようになれば、担当者の業務負担を減らしつつ、オーナーや入居者とのやり取りもスムーズに進められるようになるでしょう。
②修繕・点検業務の可視化
クラウド上で修繕履歴や点検スケジュールを一元管理すれば、進捗や対応状況をリアルタイムで共有でき、現場とオーナーの双方が同じ情報を確認できます。これにより、担当者間での報告・確認作業が効率化され、点検漏れや対応遅延の防止にもつながります。
また、写真や報告書をクラウド上に保存しておけば、過去の履歴をすぐに参照でき、修繕計画や見積判断の根拠として活用することも可能です。
情報の可視化は、単なる業務の効率化にとどまらず、管理品質の向上と予防保全の推進にも貢献します。
③入出金・会計処理の自動化
入出金や会計処理を自動化することで、日々の仕訳や照合作業を大幅に削減し、人的ミスを防ぎながら処理のスピードと精度を高めることができます。データがリアルタイムで反映されることで、資金の流れを正確に把握でき、経営判断に必要な数値をいつでも確認できるようになります。
仕組みが整えば、収益分析やオーナー対応といったコア業務に人員を集中させることも可能です。会計処理の一貫性が保たれることで、監査や金融機関への報告も円滑になり、企業としての信頼性向上にもつながります。
④部門・法人を超えた情報共有
管理業務を担う各部署や関連法人が共通のデータ基盤で情報を共有することで、現場担当から経営層までが同じ情報をリアルタイムで把握することが可能になります。
現場担当は物件の最新状況を把握したうえで修繕手配やオーナー報告を行え、経営層も現場の動きを数値で追えるようになります。
このように、部門間でデータが即時に連携する仕組みを整えることで、報告・承認・判断のスピードを大幅に高められます。結果として、オーナー対応の質や社内の意思決定精度の向上につながります。
⑤データ分析とレポートの標準化
契約・入出金・修繕などで蓄積されたデータを整備し、分析できる形に取りまとめておくことで、経営状況を正確に把握できるようになります。
契約・家賃収入・経費(光熱費・修繕費・広告費など)といった多岐にわたる項目を、クラウド上で統一フォーマットとして管理することで、データが自動で集計・反映され、常に最新の数値を確認できます。
そのうえで、レポート作成を標準化・自動化すれば、担当者による作業のばらつきをなくし、短時間で精度の高い報告が可能です。オーナーへの説明も明確になり、収支の根拠を示しやすくなります。
不動産管理クラウド導入のポイント

不動産管理業務のクラウドシステムは、業務効率化を進めるうえで欠かせないものです。
ただし、どのシステムを選んでも成果が出るわけではなく、自社の業務内容や運用体制に合った仕組みを選定することが求められます。
ここでは、不動産管理クラウドを導入する際に確認しておきたい主な視点を整理します。
現場業務への適合性
不動産管理業務のクラウドシステムを導入しても、現場で使いこなせなければ効果は得られません。どれほど高機能でも、実際の業務フローに合わなければ、入力や確認の手間が増えるだけで、現場の負担をかえって大きくする恐れがあります。
そのため、導入前の段階で契約・修繕・入出金などのプロセスを整理し、システムが現場の運用ルールに無理なく適合するかを確認することが重要です。
担当者が迷わず操作でき、日常業務に自然に組み込める設計であることが、定着と成果を左右するポイントとなります。
一元管理の範囲
不動産管理クラウドを導入する際は、どこまでの業務を一元管理の対象にするかを明確にすることが必要です。すべての部門や法人を一度に統合しようとすると、システム設計が複雑化し、現場の運用負担が増す恐れがあります。
まずは契約や入出金など、データの連携効果が大きい業務から段階的に進め、実務への定着を優先させることが大切です。そのうえで、将来的にAM・BMを含む全社的な情報連携へと拡張できる仕組みを整えておくことで、無理なく統合を進めることができます。
拡張性と法制度対応
システムの選定にあたっては、「将来の制度変更」や「業務領域の拡大」への対応も考慮することが重要です。
たとえば、電子帳簿保存法やインボイス制度など、法制度の改正は不動産管理業務に直接影響します。こういった変化に追随できる柔軟性がないと、数年後に作り直しや別システムの併用といったコストが発生する可能性があります。
拡張性の高い設計であれば、業務拡大に伴う物件数の増加などにも比較的スムーズに対応することが可能です。システム導入を単なる現状の改善と捉えるのではなく、将来的な長期投資と位置づける視点が求められます。
導入後のサポート体制
システムの導入を成功させるためには、社内に定着させ、運用を改善していくことで成果につなげていく取り組みが欠かせません。
そのため、導入後の相談や改善提案への対応など、ベンダーのサポート体制の充実度が成否を左右する大切なポイントとなります。
特に、操作に慣れていない社員や部門へのフォロー、トラブル発生時の迅速な対応などは事前に確認しておく必要があります。
さらに、将来的な事業拡張に備えて、運用支援やアウトソーシングへの対応なども見極めておきましょう。これらは、導入を単なるシステムの切り替えに終わらせず、真の業務改善へとつなげるための重要なポイントです。
不動産管理に適したクラウドサービスとは?
不動産管理業務のクラウドサービスは、契約・入出金・修繕などの日常業務を一つの仕組みでつなぎ、部門や法人をまたいで情報を共有できるかどうかが重要です。
システムの選定にあたっては、現場の運用ルールに沿って使いやすく、法改正や事業拡張にも柔軟に対応できる設計かどうかも確認するようにしましょう。
こうした要件を満たす代表的なサービスのひとつが『いい生活の不動産SaaS』です。不動産市場と不動産管理事業に特化したクラウドシステムとして、PM・AM・BMを横断してデータを一元管理できます。
また、専門スタッフによる運用支援をはじめ、担当者の負担軽減やBCP対策にも対応。導入後の伴走支援が充実しており、長期的に安心して活用できる体制も整っています。
クラウドサービスを活用して不動産管理業務を効率化

不動産管理業務の非効率は、部分的な改善だけでは限界があります。全体を見渡し、業務の流れそのものを見直すことが求められます。
契約の電子化、修繕・点検の可視化、入出金と会計処理の自動化、部門横断の情報共有、レポート標準化などを軸に、業務全体を不動産管理業務のクラウドサービスでつなぐことが近道といえるでしょう。
クラウドサービスの選定にあたっては、現場に馴染む操作性、一元管理の範囲設計、法改正への対応力、導入後のサポート体制などが基準となります。これらがそろうことで、時短だけでなく正確性と透明性が高まり、オーナー・入居者の信頼を維持しながら経営判断の質を向上させることができます。
『いい生活の不動産SaaS』などの不動産管理クラウドを活用し、現場の業務改善にとどまらず、将来的な事業拡張やBCP対策まで見据えた運用基盤の構築を実現していきましょう。











